2025年海城中社会 入試問題①
どうも。歴旅です。今日もぶらりと歴史旅。中学受験、御三家レベルの社会を楽しく学びましょう。
過去問です。総合的な問題ですね。むしろ当事者感にあふれる出題。歴史問題はあるにはありますが少ない。設問数も少ない。これは比重低め、という事でもありますが、取れるか取れないかで結構差がついてしまう出題になっています。1科目丸ごとなのでやはり落としたくないですね。しかし対策がしにくい問題です。
構造を把握していれば分かるのですが、知識ではなく、社会構造の把握が求められています。
それでは見ていきましょう。
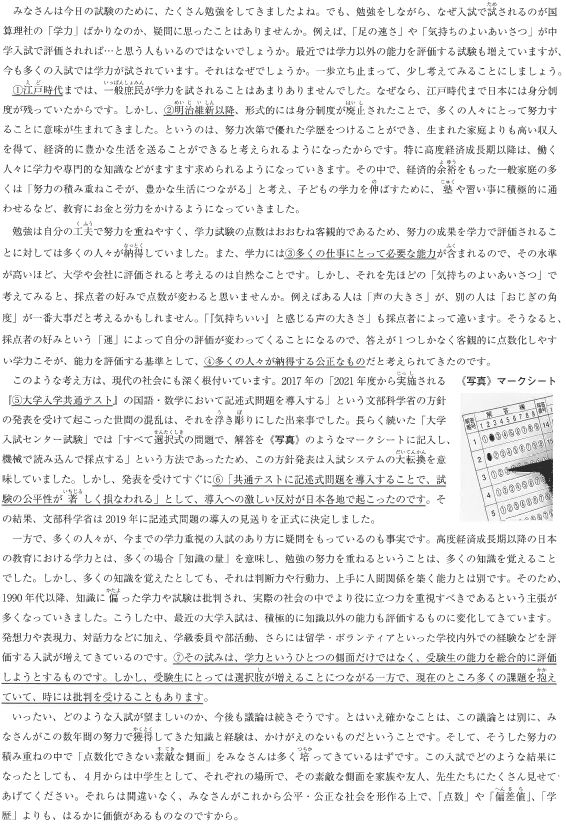
まずは長い長文があります。しかしこれ、読まなくていいですね。。
後の設問を見れば、それだけで回答していけます。
ひっかけとも言えるし、ざっくり流れを読みつつ、設問を読んでから戻っても十分です。
小論以外はある程度知識問題なので、サクサク行きましょう。
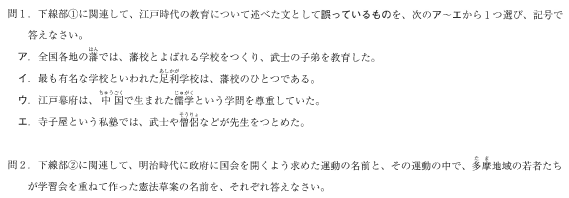
問1の回答はイです。これは簡単ですね。足利学校だけ鎌倉、南北朝なので時代が異なります。足利学校は戦国時代も注目されていて、キリスト教徒のルイス・フロイスは足利学校をねじ伏せない限りキリスト教は普及できない、という、学問の総本山として認識しています。朝廷から遠い北条氏のエリアだったとはいえ、逆に遠いからこそ、相当な見識を持つ研究所だったことが分かります。
問2は自由民権運動、五日市憲法ですね。多摩かどうかは知らなくても解答できるかと思います。明治政府は薩摩長州などの一部の人間が政治を牛耳り、山形有朋、井上薫などが汚職バンバンしていました。日本全国は戦争インフレでガタガタ、民衆は困っているのに。佐幕派の優秀な官僚達は怒り、官僚をやめたりしています。今に続く長州政権、さほど変わらないですね。
そんな状況で、日本全国の政治は日本全体を代表できる形で議員を選び、国会で議論して政治を決定しろ!という動きが起きます。それが自由民権運動です。
マルクスが出てきてから階級闘争史観が根付きます。いつも革命は農民や下層民から起きて貴族階級を打倒し、民主主義が進む、という歴史観ですが、日本には当てはまりません。自由民権運動で代表的な板垣退助も上級士族階級。むしろ日本は最高エリートから民主化を進めています。
回答は五日市憲法ですね。民間で憲法を作成するなんて、国を背負う意識のある民間の若者が多かったということです。今考えてもすごいですね。私擬憲法の議論が進んでいたのですが、のちに明治天皇が欽定憲法を選定することになったのでこの議論はなくなりました。
こうした動きは重要ですね。たとえ自分達が制定した法案が通らなかったとしても、理解度が高くリーダーシップのあるこれらの人物は新制度の中で活躍したことでしょう。
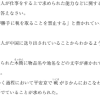

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません