平成29年渋谷幕張中学校社会②より 貨幣問題⑭ 徳川吉宗の時代⑥ 新田開発
どうも。歴旅です。今日もぶらりと歴史旅。中学受験、御三家の社会を楽しく学びましょう。
吉宗の江戸事情を見てきましたが、経済・金融に戻っていきましょう。
吉宗の経済政策
吉宗のころには年貢、主要鉱山、御林からの収入が頭打ちになり、幕府財政収支が完全に赤字になっていました。そのため様々な経済政策、改革を行いました。
・行政改革 勘定奉行の組織改編をして上方、関東を一元化。データ再編して効率化、合理化を進めました。
・新田開発 新たな税収を生み出す新田開発を精力的に実施。土木技術者も雇って公共政策ですね。
・飢饉対策 青木昆陽に命じてサツマイモ栽培研究を進めました。
・商品作物の奨励 なたね油や朝鮮人参、薬草栽培など産業化しました。
江戸時代、日本は統一してそうでしていなかった。藩は半分自治権のある連邦制で、西と東でシステムや流通、通貨も異なりました。
行政改革の一環としては、上方と関東のデータ一本化に着手したんですね。こういうバックオフィス業務や物流は一本化した方がよいです。
そしてメインはコメと通貨です。吉宗公は「米将軍」と言われるくらい、米価引き下げに苦心しました。今日は米編。
■新田開発
渋谷幕張は千葉県なので、地元の歴史知っている?ということで問われるかもしれません。印旛沼干拓という新田開発はナンバリング開発しました。享保年間から開発開始していますが、その後長く干拓は続けられます。
駅名もあるので千葉県民にはお馴染みですが、県外の人は住宅地なので知らないと思います。千葉県民も駅名で知っていても、それぞれの関係やナンバリングしていたことを知っている人はまれでしょう。
・初富(はつとみ)・二和(ふたわ)・三咲(みさき)・豊四季(とよしき)・五香(ごこう)
・六実(むつみ)・七栄(ななえ)・八街(やちまた)・九美上(くみあげ)・十倉(とくら)
・十余一 (とよいち)・十余二 (とよふた)・十余三 (とよみ)
数字とめでたい字で、印旛沼周辺を干拓していきました。
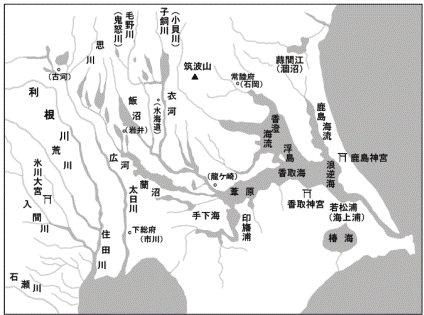
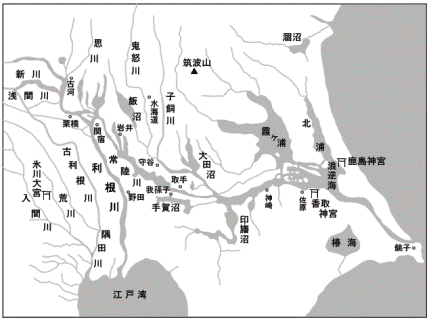
干拓によって陸地が広がっているのがわかります。
こうしてみると香取や佐原が水運で栄えていたのが容易にわかりますね。佐倉藩も交通の要衝でした。
江戸時代はちばらぎ(千葉+茨城にまたがるエリア)は農業も商業も豊かだったんです。
多くの商家が繁栄。
しかし人間の土木工事の技術には頭が下がります。私達が住んでいる土地は血と汗の結晶ですね。

江戸では大火の発生で悩まされましたが、下総では洪水に悩まされていました。沼地をいかに干すか。江戸時代、と言わず明治も昭和も干拓し、今の地形になっています。ちなみに千葉は「牧」も多いですが、極めて重要ポイントです。さて、牧はなぜ重要なのでしょうか?
ヒントは軍事力です。答えはまたどこかで笑

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません