経済の歴史① 石見銀山
どうも。歴旅です。今日もぶらりと歴史旅。
中学受験、御三家レベルの社会を楽しく学びましょう。
歴史の切口として経済の歴史があります。裏の背景や国力の差、国家経営の観点ではとても重要です。赤字財政の続く現代日本でも参考にする場面もあるので見て行きましょう。時系列は順不同で見て行きます。
まずは戦国時代、石見銀山です。
このころ世界では大航海時代真っ盛り。
ポルトガルからスペイン、そして江戸時代のオランダへと海上覇権が動いていく時代です。
この頃銀は世界貿易で活用されており、欧州、アジアを問わず流通していました。石見銀山は世界に流通する銀の10%を占めており、欧州では有名でした。いつの時代も富の源泉である中国、東南アジアの香辛料の貿易をするのに近くで銀を手に入れたかったんですね。しかし高校の世界史でもメキシコのポトシ銀山は習うのに、石見銀山は全く出てきませんね。不思議です。
同時に1543年種子島時堯(たねがしまときたか)は漂着したポルトガル人から鉄砲を2挺買いました。
弱冠24歳の当主が1億円で買ったそうです。
すごい先見の明。
そして1549年前後足利義輝と三好長慶の戦いで実戦で使われていたというのがすごい。
あっという間に分解し量産体制を作れたんですね。
この頃の鉄砲が1挺8貫500文。大体60万円強の価値です。
これ以降戦国武将の強さというのは経済力にかかってくることが大きかったのです。
さて、石見銀山ですが、最初は大内氏が所有していました。抗争によって尼子氏に所有権が移り、
その後1562年には毛利氏のものになりました。
中国地方を制した毛利元就は大大名でした。大内氏の一家臣から西日本10か国を手に入れ瀬戸内海の流通と貿易の大動脈を握る。地理的に京都から遠いとはいえ、海上交通を考えると武田信玄や上杉謙信より天下に近かったかもしれません。伊達政宗と同様弱冠年齢的に出遅れた感はあります。
しかしこの石見銀山。毛利元就は何を思ったのか石見を朝廷と幕府に献納して代官として安全に小さな利益を得ることを選びました。
なぜ天下を取れる、むしろ世界の覇権の一極を握れる石見銀山を手放したのかわかりませんが、この辺りが毛利の限界だったのかもしれません。
武将の力量としては、豊臣秀吉や徳川家康を上回る武将は数多くいました。しかし最終的に天下人となるには国家ビジョン、構想力の大きさが大きく影響したとも言えますね。

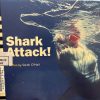
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません